1月のテーマ:子どもの特性について~マイペースな子どもの対処法~
第4回:マイペースな子どもの対処法
著者:筑波大学 准教授 水野智美先生
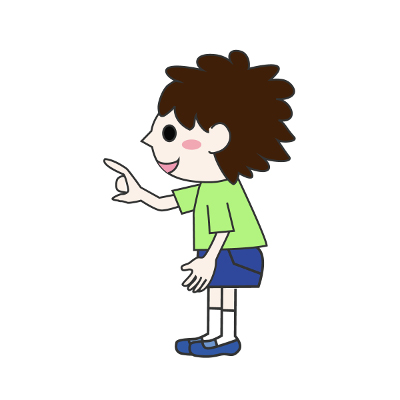 マイペースとは、周りに流されず、自分のペースで物事を進めていくことを言います。
マイペースとは、周りに流されず、自分のペースで物事を進めていくことを言います。
これは、「他人に左右されず、自分の意思で行動できる」という長所としてとらえることができます。
その一方で、周囲に気を配らずに行動するために、周りからは自分勝手に思われたり、集団行動に遅れをとってしまったりするという問題が生じることがあります。
他人に迷惑をかけず、集団行動を問題なく送ることができる範囲のマイペースであれば、「それがその子の安心できるペースである」と考えて、親は急かさずに見守ってください。
周囲から早くやるように言われると、焦ってミスが多くなってしまうとか、持っている力を発揮できなくなるといったタイプの子どもには、はじめからその子が必要とする時間を十分に確保してあげてください。
また、親に甘えたい(親に手伝ってもらいたい、自分一人ではやりたくない)ためにわざとゆっくり行動している子どもの場合には、あえて手を貸さないようにしてください。
出かける時間が迫っていると、子どもに口うるさくいいながらも、つい子どもにご飯を食べさせたり、服を着替えるのを手伝ったりする保護者の方は多いことでしょう。
子どもは「お母さんは、そう言いながらも自分のことを手伝ってくれる」と学習すると、一向に自分でやろうとしません。
この場合に、自分でやらないと自分だけ置いていかれる、誰も助けてくれないことがわかると、自分から素早く行動していくようになります。
しかし、今、自分が何をしている時なのか、いつまでにやらなくてはならないのかといった状況がわからず、やっている最中にボーっとしていたり、他のことに気をとられて手元がおろそかになってしまったりしている子どもの場合には、親はのんびり構えていてはいけません。
このタイプの子どもには、注意力が散漫になっていたら、「今、何をしている時だった?」などと声をかけて、子どもが今、やるべきことに意識が向くようにしてください。
その際に、いつもお尻を叩いて叱ってばかりいるのではなく、子どもがやるべきことに注意力が戻ったらほめたり、やろうとし始めたらほめたりして、気持ちよくその行動ができるようにすることが大切です。
また、目の前にいろいろな刺激があると、それに気をとられてしまいます。
できるだけ子どもの周りの環境をシンプルにして、やるべきことに意識がむくようにしてください。
著者紹介
水野 智美・・・筑波大学医学医療系 准教授 臨床心理士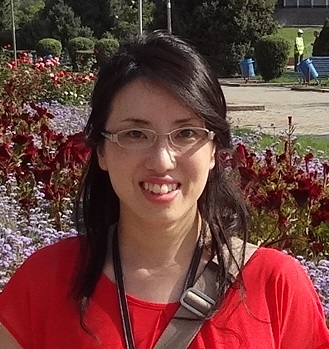 専門は命の教育、乳幼児期の臨床保育学、障害理解
専門は命の教育、乳幼児期の臨床保育学、障害理解
近年では幼児に対する命の教育や気になる子どもの対応に精力的に
過去のコラムはこちらから
1月第3回「子どもの特性について~子どもが人前で下品な言葉をわざと使うときの対処法~」を読む
1月第2回「子どもの特性について~人見知りが激しい子どもへの対処法~」を読む
1月第1回「子どもの特性について~子どもがわがままを言う時の対処法~」を読む
12月のコラム「感染症について」を読む
11月のコラム「育児のイライラ対処法」を読む
10月のコラム「乳幼児期の親子の食事について」を読む
9月のコラム「トイレについて」を読む
8月のコラム「子どもの睡眠について」を読む
7月のコラム「テレビ・ビデオの見せ方」を読む
6月のコラム「祖父母との上手な関わり方」を読む
5月のコラム「病院のかかり方」を読む









